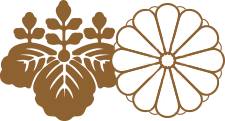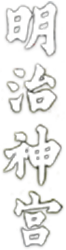明治神宮では、節分にあわせて除災招福を祈念した福豆をおわかちしています。
節分とは立春の前日、本年は2月3日にあたり、古来より豆をまくことにより、災厄を祓(はら)うといわれています。
ご家庭で豆まきをして鬼を払い、家内の安全、一年の無病息災をお祈りしましょう。
福豆は袋入りのもの、枡(ます)入りのものと2種類を各授与所でご用意しています。
枡入りの福豆には、明治神宮のお守りも入っています。
授与しておりました神棚(宮型)は、1月4日をもちましておわかちが終了となりました。

皇室の弥栄(いやさか)とわが国の繁栄、皆さまのご健康と平安をお祈り申し上げます。
明治天皇御製
まなばむとおもふみちにはことしげき
世にもいとまのあるよなりけり
(何かといそがしいこの時代であっても、学びの道を歩みたいのであれば、勉強する時間は必ずあるものである)
昭憲皇太后御歌
とりどりにつくるかざしの花もあれど
にほふこころのうるはしきかな
(色とりどりの髪飾りの花もありますが、ほのかに香るような心の誠実さこそが真の美しさというものです)
※上記の御製御歌は、正参道の桝形(ますがた)に掲げられています
■ 参拝路について
大晦日(22時30分)から1月7日にかけて、参拝路が一方通行となります。
■ おふだ・お守り・おみくじ・御朱印について
授与所(おふだ・お守り・おみくじ・御朱印等)は、下記の場所に特設いたします。
・原宿、代々木方面――参拝者駐車場(明治神宮会館前)
・参宮橋方面――西参道芝地
※大晦日(22時30分)から元日にかけては終夜開設いたします。
2日から7日までは開門(6時40分)から閉門まで開設いたします。
ただし、お手持ちの御朱印帳への記帳は午前9時から承ります。
■ 古いおふだ・お守りについて
古いおふだやお守りを納める古神符納所は、下記に設置いたします。
・南手水舎横
・各参道入口
・西芝地授与所脇
※古神符納所にお納めいただけるものは、「おふだ」「お守り」「守護矢・鏑矢」「絵馬」です。
これら以外のもの(人形・神棚・熊手・正月飾り等)はお納めいただけませんので、あらかじめご了承ください。
令和7年大晦日午後4時から令和8年1月4日まで、明治神宮には車輌が入苑できません。
1月5日(月)より入苑可能となり、車祓(車のおはらい)は1月10日(土)からとなります。
第72回全国少年新春書道展(主催・明治神宮書道会)の審査会が行われ、全国の小中学生から応募された30,184点のうち、特選300点(小学生190点、中学生110点)、準特選67点(小学生16点、中学生51点)が決まりました。
令和8年1月5日には本殿にて授賞奉告式が執行され、その後、明治神宮会館で授賞式が行われます。なお、特選作品300点は1月5日(月)より1月30日(金)まで、本殿前廻廊内で展示されます。
半切の部
八ツ切半紙の部
第72回 全国少年新春書道展作品審査内訳
献書(応募)総数 30,184作品
小学生 19,954作品 (昨年19,465作品)
中学生 10,186作品 (昨年11,128作品)
規定外 44作品 (昨年 13作品)
半切の部
特選 300点
(小学生 190点)
(中学生 110点)
準特選 67点
(小学生 16点)
(中学生 51点)
入選 1,105点
(小学生 699点)
(中学生 406点)
八ツ切半紙の部
入選 1,118点
(小学生 695点)
(中学生 423点)
■主催■
明治神宮書道会
■後援■
文部科学省、全国都道府県教育委員協議会、明治神宮、一般財団法人明治神宮崇敬会、朝日新聞社、朝日小学生新聞、朝日中高生新聞
■リンク■
※個人情報は、予め通知または公表した利用目的の範囲内で利用いたします。
事前承諾なく目的外に利用することはありません。
〒151-8557
東京都渋谷区代々木神園町1-1
明治神宮「全国少年新春書道展」係
電話:03-3379-9123
(平日9:00~17:00)
Fax: 03-3320-6059
令和8年の新年初祈願祭の法人・団体の予約を11月4日(火)より受付開始します。
元日の午前1時より神楽殿(かぐらでん)にて社運隆昌、商売繁昌、工事安全などの祈願祭をご奉仕いたします。
祈願祭時間:元 日・・・午前1時より午後5時まで
2~7日・・・午前9時より午後4時30分まで
8日以降・・・午前9時30分より午後4時まで
初穂料:「法人団体」は3万円より
※令和8年1月分の受付は終了しました
※令和8年2月以降の祈願祭の受付は承っております。お申込みはこちらから
振 込 先:みずほ銀行 青山支店
口座番号:普通1616540
口 座 名:宗教法人 明治神宮
お問合せ先:明治神宮神楽殿「参拝担当」まで
電 話:03-3379-9281
FAX:03-3373-1699

明治神宮では、「令和8年 代々木の杜カレンダー」をおわかちしています。
それぞれのページには、明治神宮の御祭神であらせられる明治天皇と昭憲皇太后が詠まれた御製・御歌が記されています。
また、境内の季節感あふれる写真が掲載されており、月ごとの明治神宮の景色を楽しむことができます(写真は令和8年1月)。
明治神宮ならではのカレンダーとなっていますので、ぜひともご活用いただければ幸甚です。
各授与所にてお求めいただけます。

——いま、明かされる明治神宮のすべて。
明治神宮の御祭神明治天皇と皇后の昭憲皇太后はもとより、創建と護持に尽くされた数多(あまた)の先人の祈りを伝える百年誌が、ついに刊行されました。(毎年1巻ずつ刊行予定。全5巻)
編 集 明治神宮
発 売 吉川弘文館
定 価 17,600円(税込)
I S B N 978-4-642-00406-0
※一般書店、または吉川弘文館(電話 03-3813-9151)でお求めになれます。吉川弘文館のサイトはこちら
論考一覧
1.「明治の宮廷文化―特に焼香水について」彬子女王殿下(京都産業大学日本文化研究所特別教授)
2.「洋装と和製としての明治憲法―国産憲法の誕生」瀧井一博(国際日本文化研究センター教授)
3.「近代日本にとっての条約改正と会議外交」五百旗頭 薫(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
4.「明治の終焉と文学―どうして漱石の『こゝろ』で語るようになったのか」山口輝臣(東京大学大学院総合文化研究科教授)
5.「17~19世紀後半の欧米にみる日本」伊藤真実子(学習院大学客員研究員)
6.「「美術趣味の普及」の時代―文部省美術展覧会をめぐって」高階絵里加(京都大学大学院地球環境学堂教授、京都大学人文科学研究所教授)
7.「外交前夜―日露戦争とポーランド」エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ(Ewa Palasz-Rutkowska)(ワルシャワ大学東洋学部日本学科教授)
8.「團琢磨―岩倉使節団の経験と世界への視点」團 紀彦(元青山学院大学総合文化政策学部教授)
9.「明治という時代の物語」朝井まかて(作家)
10.「明治天皇の時代」伊藤之雄(京都大学名誉教授)
11.「明治天皇の行幸―聖蹟でたどる」打越孝明(明治神宮国際神道文化研究所主任研究員)
12.「明治維新と御代替わり」武田秀章(國學院大學神道文化学部教授)
13.「明治神宮の神学―明治聖徳論の百五十年」佐藤一伯(明治神宮国際神道文化研究所特任研究員、御嶽山御嶽神明社宮司)
14.「明治天皇と藤波言忠―もうひとつの明治天皇紀『御逸事』をめぐって」星原大輔(大倉精神文化研究所研究部長)
15.「皇室の外交儀礼の形成過程における明治天皇」真辺美佐(立正大学文学部教授)
16.「明治天皇と御養育」岩壁義光(元宮内庁書陵部編修課長)
17.「明治天皇伏見桃山陵の造営とその意義」福尾正彦(元宮内庁書陵部陵墓調査官)
18.「維新史料編纂と明治神宮」今泉宜子(明治神宮国際神道文化研究所主任研究員)
19.「皇室と福祉―昭憲皇太后を原点として」藤本頼生(國學院大學神道文化学部教授)
20.「昭憲皇太后の行啓―聖蹟でたどる」打越孝明(明治神宮国際神道文化研究所主任研究員)
21.「明治の皇室と華族の教育」長佐古 美奈子(霞会館記念学習院ミュージアム学芸員)
22.「皇后の祈り―祭祀儀礼と昭憲皇太后」小平美香(学習院大学講師、國學院大學日本文化研究所共同研究員、天祖神社宮司)
23.「昭憲皇太后と津田梅子―女子教育をめぐる奇しき縁」髙橋裕子(津田塾大学学長)
24.「昭憲皇太后大礼服研究修復復元プロジェクトを振り返る」モニカ・ベーテ(Monica Bethe)(中世日本研究所所長)
25.「皇太后としての1年8カ月―明治天皇をお偲びして」米窪明美(元学習院女子中等科・高等科講師)
26.「明治神宮御祭神としての昭憲皇太后」廣瀬浩保(明治神宮禰宜、百年誌編纂室室長)
27.「明治神宮の祭祀学―祭日を手がかりに」佐藤一伯(明治神宮国際神道文化研究所特任研究員、御嶽山御嶽神明社宮司)
28.「帝都東京における〈祈りの公共空間〉としての明治神宮内外苑」藤田大誠(國學院大學人間開発学部教授)
29.「皇室と明治神宮―明治神宮に参拝された皇族方」佐藤一伯(明治神宮国際神道文化研究所特任研究員、御嶽山御嶽神明社宮司)
30.「『社務日誌』から見える初詣の諸相」平山 昇(神奈川大学国際日本学部准教授)
31.「明治神宮祈願祭における祈り―祈願数の時系列分析」望月泰博(早稲田大学データ科学センター講師)
32.「明治神宮の人生儀礼―七五三の変遷をとおして」田口祐子(一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団冠婚葬祭総合研究所研究員)
33.「第五代宮司鷹司信輔と明治神宮の戦後復興」鷹司尚武(神社本庁統理)
34.「明治神宮の雅楽」遠藤 徹(東京学芸大学教育学部教授)
35.「歌に詠われた明治神宮―御製御歌を中心に」永田和宏(歌人、宮中歌会始詠進歌選者、明治記念綜合歌会常任委員)
36.「明治神宮献詠会と明治記念綜合歌会―明治神宮における献詠の歴史と現在」宮本誉士(國學院大學研究開発推進機構教授)
37.「宮中の和歌―御集編纂の歴史と明治神宮」豊田恵子(宮内庁書陵部主任研究官)
38.「和歌のおみくじ・唱歌・神楽舞―「大御心」の展開と戦後の明治神宮」平野多恵(成蹊大学文学部教授)
39.「和歌披講の世界」園池公毅(宮中歌会始披講会理事、早稲田大学教育・総合科学学術院教授)
40.「明治天皇の御製碑について―附 昭憲皇太后の御歌碑」打越孝明(明治神宮国際神道文化研究所主任研究員)
41.「戦後の歌壇と明治神宮」岡野弘彦(歌人、明治記念綜合歌会顧問)
42.「明治神宮所蔵の宸筆による御製と親筆の御歌」黒田泰三(明治神宮ミュージアム館長)
43.「明治神宮の「祭り」と明治神宮崇敬会―式年鎮座祭と崇敬会奉賛活動の軌跡」中島精太郎(明治神宮名誉宮司)
44.「まつりを繋ぐ、郷土を繋ぐ―民俗芸能の明治神宮奉納をめぐって」久保田裕道(東京文化財研究所無形民俗文化財研究室長)
45.「次代を育む杜―明治神宮の青少年育成と福祉事業」今泉宜子(明治神宮国際神道文化研究所主任研究員)
46.「武士道精神の復興と継承―内苑に開設された「至誠館」の使命」稲葉 稔(武道場至誠館名誉館長)
47.「明治神宮の編纂事業―『明治天皇詔勅謹解』と『大日本帝国憲法制定史』を中心に」戸浪裕之(明治神宮国際神道文化研究所研究員)
48.「国際交流・海外研究助成・宗教間対話―グローバル社会における明治神宮」伊藤守康(明治神宮禰宜、明治神宮国際神道文化研究所国際事業課長)
49.「国際貢献と明治神宮―「昭憲皇太后基金」を通じた実践」アイシャ・マンスール・ロー(Aicha Mansour LO)(昭憲皇太后基金合同管理委員会事務局)
50.「相撲と明治神宮―国技の継承と神事の伝統」八角信芳(日本相撲協会理事長、相撲博物館館長代行)

ミャンマー地震の発生を受け、救援金の募金箱を境内に設置したところ、ご参拝の皆様からご協賛をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
お寄せいただいた救援金は明治神宮崇敬会の福祉事業献金と合わせて600万円となりました。6月25日、御神前に奉告申し上げ、明治神宮崇敬会副会長の川﨑里子氏から、日本赤十字社社長・清家篤氏に手交いたしました。
皆様のまごころは日赤により、被災地に届けられます。
ご協力ありがとうございました。

5月30日、明治神宮にて大の里関の横綱推挙状授与式が行われ、日本相撲協会の八角信芳理事長より推挙状と横綱が授与されました。
その後、授与されたばかりの横綱を締めて雲竜型(うんりゅうがた)の土俵入りを奉納しました。
雨天につき手数入の奉納場所が御社殿となり、収容人数の都合上、一般参拝者は陪観いただくことができませんでしたが、開門(朝5時)から楽しみにいらっしゃった方々をはじめ約1,000人の参拝者が見守り、時折大きな声援が上がる中、力強い奉納が行われました。