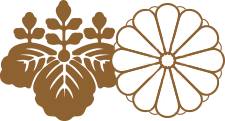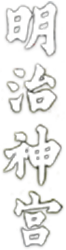5月2・3日に「春の大祭」が行われます。
祭典では、世界平和を祈る昭和天皇の御製(ぎょせい)からつくられた神楽「浦安の舞」が舞われます。
-
5月2日(金) 午前10時 春の大祭 第一日の儀 5月3日(土・祝) 午前10時 崇敬者大祭
最新のお知らせは最新情報に記載しております。
下記「明治神宮最新情報はこちら」もご確認ください。
大祭期間中は、「舞楽」や「能・狂言」などさまざまな伝統芸能が奉納されます。
※雨天の場合、奉祝行事等場所が変更になります。
- 奉祝行事(予定)
-
4月29日(火・祝) 午前11時 舞楽 於:神前舞台 5月2日(金) 午前11時45分 能・狂言 於:神前舞台 5月2日(金) 午後3時45分 邦楽邦舞 於:神前舞台 5月3日(土・祝) 午前9時 弓道大会 於:武道場至誠館第二弓道場 5月3日(土・祝) 正午 三曲 於:神前舞台 5月3日(土・祝) 午後2時30分 薩摩琵琶 於:神前舞台
4月29日(火・祝) 午前11時 舞楽 神前舞台

奉納/楽友会
※写真はイメージです
「振鉾(えんぶ)」
舞楽会(ぶがくえ)の最初に舞われる曲です。天地の神々と先霊を祀る意味があるとされています。左右の舞人が一人ずつ、笛・太鼓及び鉦鼓(しょうこ)だけの伴奏で舞います。周の武王(ぶおう)が天下の平定を誓った光景といわれています。
「陵王(りょうおう)」
陵王は、舞楽の最も代表的な作品で、しばしば演奏される名曲です。
中国の北斉(550~577年)の蘭陵王長恭(らんりょうおうちょうきょう)は、容姿がたいへん美しかったので、常に厳しい仮面をつけて戦場に臨んでいたといわれています。ある時、周の大軍を金墉城(きんようじょう)にて破り、勇名は天下にとどろきました。この曲は、この故事にのっとり、その姿を舞にしたものと伝えられています。
左方の一人舞で、舞人は竜頭を頭に乗せた面をつけ、毛縁(けべり)の裲襠装束(りょうとうしょうぞく)を着用し、金色の桴(ばち)を右手に持って勇壮華麗に舞います。
「白浜(ほうひん)」
またの名を「栄円楽(えいえんらく)」ともいいますが、この曲の由来等の詳細は不明です。
右方の四人舞で、舞人は蛮絵装束(ばんえしょうぞく=唐獅子の刺繍のある袍をつける装束)を着て、巻櫻(けんえい)の冠を被り、緌(おいかけ)を付けて舞います。始めに高麗笛(こまぶえ)と篳篥(ひちりき)の音頭が無拍子の序吹(じょふき)を奏し、途中から拍子のある楽となり、全員の演奏となった後、舞人が登台し、出手(ずるて=舞台に登った時の所作) を舞い立ち定まり、つづいて当曲舞となります。
なお、曲の中程で跪(ひざまず)き、右肩を袒(ぬ)ぎ、舞いながら舞台を一回りします。
伴奏は高麗双調(こまそうじょう=洋楽のイ音(A音)に相当する音を基音とする調子)の曲です。
「長慶子(ちょうげいし)」
醍醐天皇の孫・源博雅(みなもとのひろまさ)の作といわれている名曲で、慶祝の意を表し、慣例として舞楽会の結びに奏されます。曲だけで舞はありません。
5月2日(金) 午前11時45分 能・狂言 神前舞台

奉納/能楽協会
※写真はイメージです
半能「高砂(たかさご)」
高砂は松の緑と人の生命の長さ、治まれる世のめでたさを重ねて、祝言能らしいのびやかで荘重な名曲です。
今回はこの能の後半を演じます。阿蘇宮の神主友成は舟で住吉へ行くと、月下に住吉明神が現れ、宮人達の奏でる神楽につれて颯爽と神舞を舞い、聖代長久、国家安泰を祝福します。
狂言「文荷(ふみにない)」
左近三郎(さこのさむろう)という少年に手紙を書いた主人は、太郎冠者(たろうかじゃ)と次郎冠者(じろうかじゃ)に届けるよう言いつけます。
道中交互に文を持っていましたが、竹に結いつけて二人で持つことにしました。ことのほか重い文なので「恋重荷(こいのおもに)」の謡を謡いながら歩くうち、中を見たくなってしまい、文を開いて見てしまいます。あげくの果ては奪い合いになり文が裂けてしまいます。一計を案じ扇であおいで届けようとしますが、そこへ主人がやって来てその様子を見られてしまい……。
■高砂 半能(金剛流)
【シテ】種田 道一
【ワキ】大日方 寛
【ワキツレ】野口 能弘 野口 琢弘
【笛】栗林 祐輔
【小鼓】大村 華由
【大鼓】安福 光雄
【太鼓】安福 光雄
【後見】廣田 幸稔
【地謡】金剛 龍謹 坂本 立津朗 元吉 正巳
田村 修 惣明 貞助 見越 英明
■文荷 狂言(大蔵流)
【シテ】山本 則秀
【アド】山本 泰太郎 山本 則重
【後見】山本 凜太郎
5月2日(金) 午後3時45分 邦楽邦舞 神前舞台

奉納/日本舞踊協会、長唄協会
※写真はイメージです
長唄「七福神(しちふくじん)」
江戸市村座(えどいちむらざ)で初演され、長唄の中でも最も古い曲の一つと言われています。「七福神」の名前の通り、おめでたい踊りとして、よく上演される人気の曲です。古風ながらもにぎやかな趣向も盛り込まれていて、特に間の早いところは、踊りとしての見どころでもございます。
長唄「君が代松竹梅(きみがよしょうちくばい)」
松竹梅を詠みこんだ曲はいくつもありますが、その中でも代表的な曲です。三代目杵屋正次郎(きねやしょうじろう)による作曲で天保14年に初演され、歌い出しから「君が代松竹梅」と呼ばれています。格調の高さの中に、華やかさとやわらかい雰囲気もあり、変化のある踊りと曲が楽しめます。
■七福神
立方 尾上 菊透
■君が代松竹梅
立方 坂東 はつ花
【唄】杵屋 喜三郎 杵屋 巳之助 杵屋 喜太郎
【三味線】稀音家 祐介 今藤 政十郎 東音 阪本剛二郎
【小鼓】藤舎 呂秀
【脇鼓】望月 大貴
【大皷】望月 左太助
【太鼓】藤舎 円秀
【笛】福原 徹彦
5月3日(土・祝) 午前9時 明治神宮奉納遠的弓道大会 至誠館第二弓道場

奉納/東京都弓道連盟
※写真はイメージです
5月3日(土・祝) 正午 三曲 神前舞台

奉納/日本三曲協会
※写真はイメージです
山田流箏曲「御代万歳(みよまんざい)」
大正天皇ご即位の記念祝賀曲として、大正5年に今井慶松(いまいけいしょう)が作曲、吉丸一昌(よしまるかずまさ)作詞。今井慶松は三代・山勢松韻門下で東京音楽学校教官を山勢から引き継ぎ、皇室の慶事記念作品も「御苑生の竹(みそのふのたけ)」「鶴寿千歳(かくじゅせんざい)」「十返りの松(とかえりのまつ)」など多数あります。
この「御代万歳」の前弾きはおめでたい雰囲気の「楽」で始まり、「君が代」の旋律が意識されています。最初の合(あい)の手には「六段調」を合わせ、後半の合の手は「三番叟(さんばそう)」の手を用いるなど、全編を通し祝意の溢れる構成となっています。
都山流本曲「平和の山河(へいわのさんが)」
昭和26年8月、流祖中尾都山(なかおとざん)作曲。
終戦後、平和条約が締結され、日本人の心の中にも、ようやく独立と平和の喜びを得た時の記念の曲です。流祖が、荒涼とした広島を訪れた際、心底の平和を願う気持ちから生まれた尺八二部合奏曲です。昨今の地球では、いくつかの地域で戦争・紛争が続いておりますが、1日でも早く終結し、平和な山河(世の中)になることを願っています。
■山田流箏曲「御代万歳」
山勢松韻 社中
■都山流本曲「平和の山河」
都山流尺八楽会 社中
5月3日(土・祝) 午後2時30分 薩摩琵琶 神前舞台

奉納/友吉鶴心
※写真はイメージです
曲名:壇の浦(だんのうら) 鶴田錦史/改編・作曲
今から840年前、治承・寿永の乱。
平家一門は滅び行き、源氏の世に移り行く、決戦を物語った作品です。