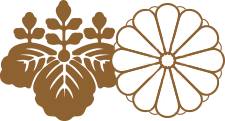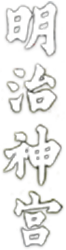7月

ノコギリクワガタ
夜の参道に、立派なアゴを持ったノコギリクワガタがいました。(令和5年7月13日撮影)

ウバユリ
西参道の入口付近で、ウバユリが開花していました。 (令和元年7月19日撮影)

ミドリハカタカラクサ
武道場至誠館の向かいにミドリハカタカラクサの花が咲いていました。 (令和元年7月19日撮影)

ノカンゾウ
宝物殿前の芝地でノカンゾウが開花していました。濃いオレンジ色で夏の兆しが感じられました。 (令和元年7月10日撮影)

マヤラン
マヤランが咲いているのを見つけました。漢字名・摩耶蘭は、神戸市の摩耶山で発見されたことが由来だそうです。 (令和元年7月10日撮影)

カワセミ
南池を見ていたときのことです。近くの枝にカワセミが飛んできました。 (令和元年7月17日撮影)

ヤマユリ
正参道でヤマユリが咲いていました。人よりも草丈が高く、支柱を施していました。 (令和元年7月11日撮影)

タシロラン
漢字名、田代蘭。明治時代に田代善太郎氏が発見したことで命名されたとのことです。 (令和元年7月2日撮影)

ヤブミョウガ(花)
参道や車道脇にヤブミョウガが咲いていました。葉がミョウガに似ているのが名の由来です。(平成30年7月20日撮影)

ヤブミョウガ(葉)

カブトムシ
カブトムシが、社務所の軒下にいました。境内で羽化したのでしょうか。 (平成30年7月9日撮影)

ノカンゾウ
芝地に咲いていました。50センチほどの草丈です。 (平成30年7月12日撮影)

ヤマユリ
正参道でヤマユリが咲いていました。 (平成30年7月2日撮影)

ニホントカゲ
御苑を歩いていたら二ホントカゲに出会いました。さっと木陰に逃げて行きました。 (平成30年7月2日撮影)

オオミヤマトンビマイ
大きなスダジイの根元に、大きなキノコが生えていました。 (平成30年7月2日撮影)

ヤブミョウガ
ヤブミョウガの花が咲いていました。ミョウガの葉と似ていることから命名されたそうです。 (平成29年7月27日撮影)

エゴノキ
西参道沿いでエゴノキが実をつけていました。 (平成29年7月27日撮影)

ミズキ
ミズキの実をカラスがついばんでいました。 (平成29年7月27日撮影)

タシロラン
車道脇にタシロランが生えていました。林内の日陰に多く見られました。 (平成29年7月3日撮影)

カルガモ
南池・御釣台の脇にカルガモがいました。一年中同じ地域で生活する、留鳥です。 (平成28年7月23日撮影)

ノハラアザミ
菖蒲田付近にノハラアザミが生えていました。人の背丈ほどの高さと、葉や茎のとげが印象的です。 (平成28年7月23日撮影)

キツネノカミソリ
御苑にキツネノカミソリが咲いていました。葉は、花が咲く頃に枯れてしまいます。 (平成28年7月23日撮影)

ヒヨドリジョウゴ
ヒヨドリジョウゴが開花していました。他の植物に巻きついて生長する、弦(つる)植物です。 (平成28年7月23日撮影)

ツユクサ
花は半日でしぼんでしまいます。染料に使用していたことなどから、色がつく「着草(つきくさ)」が転化したのが名の由来だそうです。 (平成28年7月23日撮影)

ノコギリクワガタ
北参道沿いの燈籠(とうろう)にノコギリクワガタがいました。大きな角が印象的でした。 (平成28年7月1日撮影)

シラカシ
参道沿いの木々にどんぐりが結実しています。シラカシは1年、スダジイは2年目に成熟します。(平成28年7月19日撮影)

スダジイ

ウバユリ
境内でウバユリが咲いていました。大きなものは、人の背丈ほどの高さになります。 (平成28年7月20日撮影)

ハエドクソウ
漢字で書くと、蝿毒草。根を煮詰め、その汁でハエ取り紙をつくっていたのが由来だそうです。別名「ハエトリソウ」とも呼ばれます。(平成27年7月22日撮影)

イヌビワ
実の味が、ビワより味が劣るためにこのように名づけられたようです。実際は、クワ科イチジク属。境内では、変種のホソバイヌビワも見ることができます。(平成27年7月31日撮影)

ホソバイヌビワ

ヨツバヒヨドリ
上からのぞきこむと交互に対生した葉が四つに見え、細かい花の集まりが鳥類のヒヨドリの頭部のようだから、と命名されたそうです。南池の四阿(あずまや)周辺で見ることができます。(平成27年7月10日撮影)

ミズヒキ
のし袋や贈答品に使われる水引(みずひき)を思わせるため、ミズヒキという名になったそうです。西参道沿いで咲いているのを見ることができます。(平成27年7月14日撮影)

オオゲジ
境内施設の天井に、オオゲジがいました。ゲジ(通称ゲジゲジ)の大型種。環境の変化に敏感で、個体数も少ないといわれています。(平成27年7月14日撮影)

アオスジアゲハ
御苑でアオスジアゲハが舞っていました。黒と青緑色の羽が目立ちます。幼虫はクスノキの葉を好むとのこと。明治神宮で生まれ、羽化したのでしょうか。(平成27年7月14日撮影)

セイヨウアジサイ
客殿裏にある桜の木の根元でセイヨウアジサイが咲いていました。梅雨の訪れを感じますね。(平成25年7月5日撮影)

タシロラン
今年も境内のあちこちでタシロランが咲きはじめました。明治神宮の杜が豊かである象徴だそうです。(平成25年7月5日撮影)