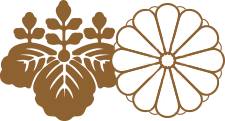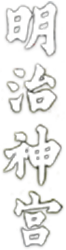8月

テッポウユリ
社務所の入口前に、大きくて白いテッポウユリの花が咲いていました。(令和5年8月14日撮影)

カヤタケ
今はまだ丸いカヤタケのカサは、成長するにつれ反り返っていきます。(令和4年8月25日撮影)

ノウタケ
正参道から外れた小径を歩くと、幼いノウタケがいくつも顔を出していました。(令和4年8月24日撮影)

ノシラン
御苑の入口にノシランの花が咲いていました。第二駐車場付近でも開花しています。 (令和元年8月31日撮影)

ウバユリの実
7月に開花していたウバユリが実を着けていました。成熟すると割れて種が出てきます。(令和元年8月31日撮影)


ナナフシ
ナナフシを見つけました。社務所前の縁石を歩いていました。 (令和元年8月8日撮影)

タカサゴユリ
社務所の入口でタカサゴユリが開花していました。草丈が1.5メートルほどにもなるユリの仲間です。 (令和元年8月13日撮影)

赤とんぼ
境内の植物に赤とんぼがとまっていました。秋の兆しを感じさせる生きものですね。 (令和元年8月19日撮影)

エゴノキ
エゴノキに実がなっていました。すでに落下していたものもありました。 (平成30年8月31日撮影)

ヤブラン
境内でヤブランを見つけました。穂状に花がたくさんついています。 (平成30年8月31日撮影)

ウバユリ
筒状で目立たない花です。代々木口の近くに咲いていました。 (平成30年8月1日撮影)

セミの抜け殻
セミの抜け殻を見つけました。明治神宮にはセミの仲間が6種います。 (平成30年8月1日撮影)

カブトムシ
カブトムシのメスでしょうか。シラカシの木にいました。 (平成30年8月1日撮影)

サンゴジュ
サンゴジュの実が熟していました。社務所の周辺で撮影しました。 (平成30年8月2日撮影)

タカサゴユリ
社務所の入り口にタカサゴユリが咲いていました。人よりも草丈が高いのが印象的です。 (平成30年8月7日撮影)

イヌビワ
西参道沿いのイヌビワが熟していました。類似種のホソバイヌビワもあります。(平成30年8月10日撮影)

ホソバイヌビワ

チャノキ(茶の木)
隔雲亭の近くに、チャノキがありました。果実は熟すと三つに割れます。 (平成29年8月29日撮影)

アブラゼミ
境内で鳴き声を聞くことの多いセミの仲間です。サクラの木にとまっていました。 (平成29年8月29日撮影)

ニホントカゲ
南池の近くにニホントカゲがいました。素早くしげみに隠れてしまいました。 (平成29年8月18日撮影)

シオカラトンボ
北池のほとりと芝地を行き来していました。若いオスは黄色っぽく、ムギワラトンボ(麦わらとんぼ)の別名があります。 (平成28年8月30日撮影)

カジノキ
カジノキが橙色の果実をつけはじめていました。樹皮の繊維は和紙の原料に使用していたそうです。 (平成28年8月30日撮影)

ヘクソカズラ
ヘクソカズラにオリーブ色の実ができていました。太い茎が目立ちますが、つる性で草の仲間です。 (平成28年8月30日撮影)

ムクロジ
宝物殿前芝地のムクロジに実がなりはじめていました。熟した果皮に含まれるサポニンは泡立ちがよく、石鹸として使っていたことがあるそうです。 (平成28年8月30日撮影)

イヌビワ
西参道沿いで、イヌビワの実がなっていました。熟すと黒くなります。 (平成28年8月30日撮影)

セミの羽化
参道沿いの木で、セミが羽化していました。アリやハチなどの天敵を避け、夜間に脱皮し飛び立つそうですが、境内では時折、朝方や夕方でもみかけることがあります。 (平成28年8月10日撮影)

ミズキ
参道沿いや芝地で、ミズキの実が熟していました。先日、カラスがついばんでいましたが、他にも、ヒヨドリやムクドリも好んで食べにきます(平成27年8月31日撮影)

ヘクソカズラの実
本種の花期は8月から9月ですが、早いものは、もうオリーブ色の実をつけはじめていました。(平成27年8月31日撮影)

ツマグロヒョウモン
芝地を舞う、ツマグロヒョウモンというチョウに出会いました。周りに咲いていた、キツネノマゴの花の蜜がお目当てなのでしょうか。(平成27年8月31日撮影)

キツネノカミソリ
御苑でキツネノカミソリが咲いていました。葉の形を剃刀(かみそり)に見立てたことが名前の由来だそうです。(平成27年8月6日撮影)

シラカシ
境内では、早くも若いどんぐりが落ちています。シラカシ、コナラをはじめとしたどんぐりは1年で成熟しますが、クヌギやスダジイなど、2年目の秋に熟すものもあります。(平成27年8月6日撮影)

コナラ

クヌギ

クロアゲハ
クロアゲハが、ムラサキシキブの周りを忙(せわ)しなく飛んでいました。吸蜜しているのでしょうか?(平成27年8月12日撮影)

キツネノマゴ
芝地や参道脇にキツネノマゴが咲いています。人のくるぶしにも満たない丈のもの、膝下くらいの高さのものなど、草丈に個体差があります。(平成27年8月12日撮影)

ノシラン
「熨斗蘭」と、名に蘭がついていますがユリ科の仲間です。御苑北口に咲いていましたが、本来、関東には自生しない植物だそうです。(平成27年8月19日撮影)

イチモンジセセリ
北池周辺を、数匹のイチモンジセセリが飛び交っていました。この種の仲間は、他のチョウに比べ敏速に飛ぶことや、ガに容姿が似ていることが特長だそうです。(平成27年8月19日撮影)

ヒヨドリジョウゴ
南池でヒヨドリジョウゴの花が咲き、実が生っていました。反り返った花冠が印象的で、実は熟すと黒くなるようです。(平成26年8月19日撮影)

キツネノマゴ
境内のあちこちでキツネノマゴが咲いています。小さな唇形の花がかわいらしいです。(平成25年8月27日撮影)