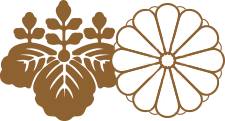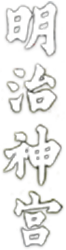明治天皇崩御後のご生活
青山御所における昭憲皇太后の日常のご生活は、朝6時にご起床、女官奉仕のもと化粧室にて、御口を漱(すす)ぎ、御髪(おぐし)をあげられて、着替えを済まされて拝所にお入りになり、皇祖皇宗(こうそこうそう)の御霊(みたま)を拝し、ついで先帝の御霊にお参りされるのを例としました。また、御霊前に供えまつる御供膳(ごきょうぜん)などはすべてご自身でなさり、いっさい女官の手を借りられませんでした。御拝(ごはい)をすまされると、朝食を召し上がられ、その後は読書、ご作歌、軽いご散策に日々を過ごされたということです。
明治天皇がご生前お好みであった品々や、年の初物、御苑より送られた野菜、臣下からの献上品のめずらしいものはまず御霊前に供えられました。沼津御用邸にご滞在中も、祭壇を設けて供物を供えられ、決して他人まかせにされず、草花などめずらしいものが献上になったり、土筆(つくし)や蕨(わらび)などの初物を献上するものがあれば、ただちに先帝の御霊前に供えられ、その後ご覧になるのでした。また、崩御されるまでの3年間、鳴物(なりもの)はもちろん蓄音機もお使いにならず、慰(なぐさ)みごとなどは一切なさらなかったということです。
これまでのご公務のすべては皇后(貞明皇后)がお引継ぎになったため、皇太后は、まったく世事(せじ)に関わられずに静かな生活を送られていました。しかし、赤十字病院の貧困患者に施療補助費と、毎年1月の寒い時節に衣服地と裁縫料を下賜(かし)されることだけは、皇后時代より引き続きお続けになり、国民に福祉の手をさしのべられたのでした。
【青山御所】
(宮内庁宮内公文書館所蔵)