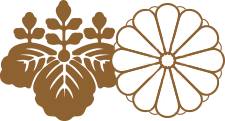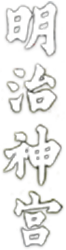ろうそくの光
千萬(ちよろず)の民の心ををさむるも
いつくしみこそもとゐなりけれ(明治天皇御製)
宮中では、儀式や招宴などの公式行事がおこなわれる正殿・豊明殿(ほうめいでん)には電灯が設備され、シャンデリアが煌々と輝いていましたが、天皇がお休みになる奥の御座所は電灯の代わりにロウソクをお使いになりました。これは文明が発達しても昔の不自由な時代を忘れず、質素倹約を守らなければならないということを側近や国民にさとすために、ご自身が模範をお示しになったものですが、それ以外にも頑なにロウソクを使用する理由がもう一つあったといわれています。
「電灯が明るくて便利なことはよくわかっているが、いま急にロウソクをやめて電灯に換えてしまうと、そのために困るものが出てくる。まあ、このままでよろしい」
と、天皇がよく話されたことの背後には、何か特別なお気持ちがあったようです。
じつは、宮中には経済的にあまり豊かでない人々も奉仕しており、小さくなったロウソクはいずれ彼らに配られることになっていました。天皇はその事情をご存知でしたから、こうした人々のことを気づかっておられたのです。奥の御座所の障子はロウソクの油煙のために黒ずんでしまい、室内は昼でもうす暗くなっていたそうですが、破れたところをつぎはぎすることはあっても張り替えはなさらなかったといわれています。天皇が崩御になったとき、障子紙の一片を頂戴した側近の栗原廣太(くりはら ひろた)は、「農家の台所の障子紙でもこんなに黒くはならないだろう」と、天皇のご生前の質素な生活ぶりをあらためてお偲び申し上げたとのことです。
また、宮中の暖房については、宮殿にはスチームの設備が備わっていましたが、御座所にはこうした設備がなく、天皇は冬になると火鉢をお使いになりました。夏の冷房はもちろん、氷柱や扇風機などもほとんどお使いにならなかったようです。
【明治天皇御料 三枝燭台(明治神宮蔵)】